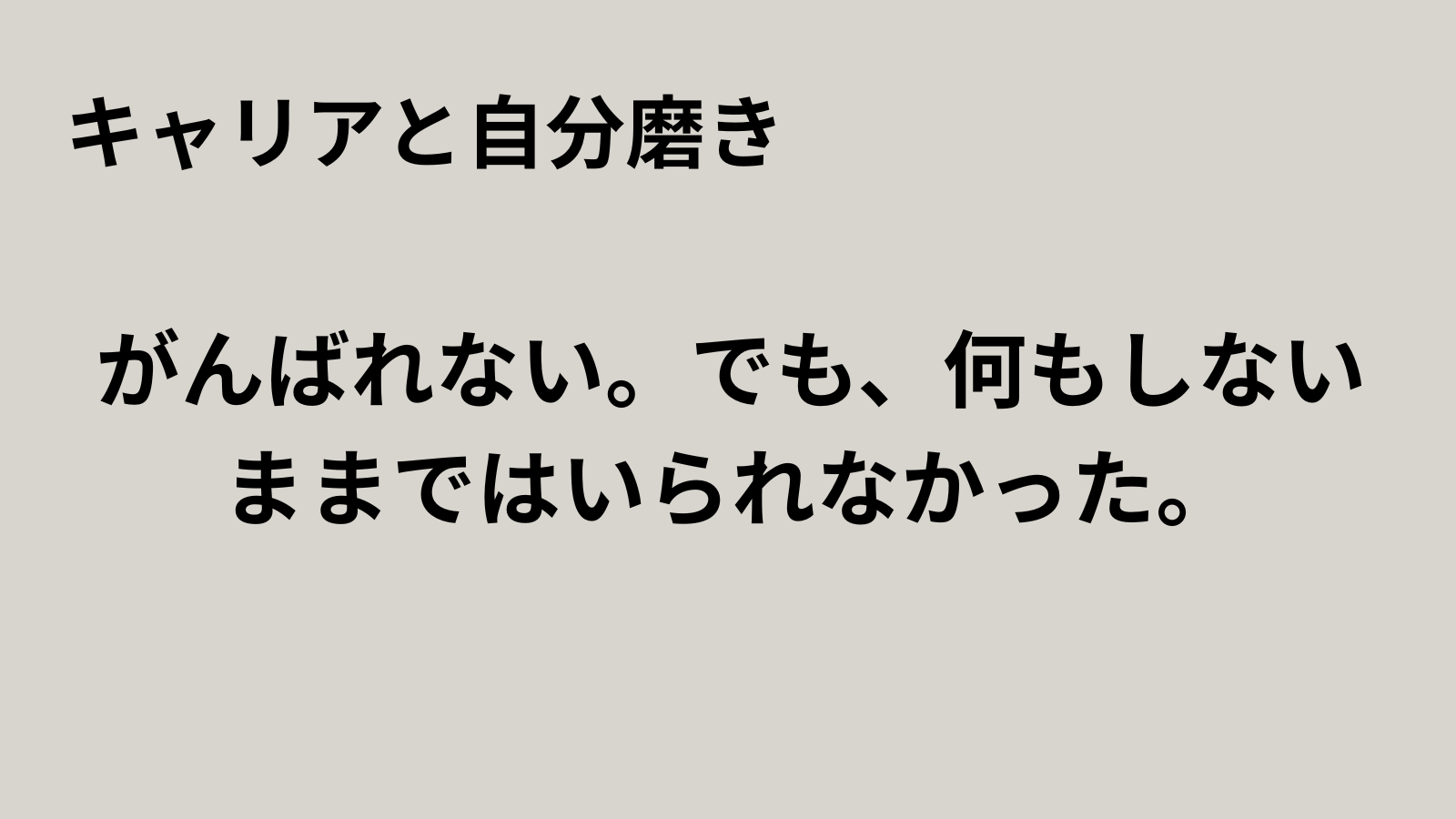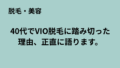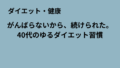※当サイトでは、アフィリエイト広告を利用しています。
記事は筆者の体験と調査をもとに構成したもので、感じ方や効果には個人差があります。
あくまで参考情報のひとつとして、お読みいただければうれしいです。
これは、「副業を始める話」ではなく、「がんばれない自分でも、前に進める道を探した話」です。
40代になって、ふと「副業しなきゃ」と思うようになりました。
でも、すぐに動けたわけではありません。むしろ、動けませんでした。
今思えば、「がんばる」ことに疲れていたのかもしれません。
本業ではやりがいを感じなくなり、会話も減り、社内では“空気”のような存在になっていました。
むすめたちは成長し、これからどんどんお金がかかっていきます。
「このままでいいのか?」という焦りと、「でも無理はできない」という現実が、心のなかでせめぎ合っていました。
社内失業と、静かに押し寄せる不安
数年前までは、それなりに忙しく働いていました。
でもある時期から、明らかに“必要とされなくなった”と感じるようになりました。
上司との会話も減り、振られる仕事も雑務ばかり。
会社にいるけれど、何かが止まっているような感覚でした。
転職も考えました。実際、何度か活動もしました。 でも、年齢的に求められるマネジメント経験が足りないとのフィードバックも受けましたし、面接も正直得意ではなかったです。 結果として、「今の会社にいながら、別の道も育てておきたい」と考えるようになりました。
“がんばれない”という現実
正直に言えば、がんばれないです。 子育ても家事もあるし、加齢のせいか、ひと晩寝ても疲れが取れにくくなってきました。
だから、「がんばって副業しよう」では、続かないとわかっていました。
やるなら、“がんばらなくても進む方法”を選ぶしかありませんでした。
AIとの出会いがくれた転機
ある日、なんとなくChatGPTに話しかけてみました。
すると、思った以上に会話が成立して、驚きました。
社内ではほとんど人と話さない日もありました。
でもAIとは、何度でも思考を整理しながら話ができました。
「このままでいいのか?」という問いに対して、
無理に励ますことはせず、でも整理された答えを返してくれる存在。
たとえば、「現状の課題は何だと思いますか?」「どのような状態を目指したいですか?」といった問いかけを受けて、漠然とした不安が少しずつ具体的な課題として整理されていきました。自分のなかでモヤモヤしていて言語化できなかった部分が、ChatGPTとの会話を通じて少しずつ言語化されていくのを感じました。そんな会話を続けていくうちに、「じゃあ、まずできることからやってみようかな」と、少しずつ気持ちを前に向けてくれました。
副業を“選ぶ”前に、整えたこと
副業について調べると、「せどり」「ライター」「バイト」「動画編集」など、いろいろな選択肢が出てきます。
でもどれも、自分には合いませんでした。
せどりは過去にやってみたことがありますが、荷物を一時的に家に保管しなければいけないので家庭に影響するし、何よりフロー型でしんどかったです。 アルバイト系も、自分が動けなければ収入が止まってしまいます。
わたしが求めていたのは、
- 時間や場所に縛られないこと
- 家族との時間を犠牲にしないこと
- 自分が動かなくても収益が出る“仕組み”
- テクノロジーと相性がいいこと
そんな条件を重ねていった結果、
「AIを使ったブログ運営」という選択肢が浮かび上がってきました。
まとめ:“がんばらない副業”という選択
副業は、無理して始めるものではありません。
焦って選んで、燃え尽きてしまったら意味がありません。
まずは、自分の気持ちや生活に合った形に“整える”。
そのうえで、自分に合った道を少しずつ育てていく。
まるおにとっては、それが「ブログ」と「AI」との付き合い方でした。
次回からは、そんな『AIを使ったブログ運営』の具体的な始め方について、わたしの試行錯誤を交えながら詳しく紹介していきます。特に、“がんばらなくても続けられる”ためのAI活用の工夫や、今まさにわたし自身が試している収益化に向けたステップについても、等身大でお伝えしていく予定です。
40代。がんばらなくても、進む方法はあります。
あなたにも、そう思ってもらえたらうれしいです。
わたしの体験が、あなたのヒントになればうれしいです。
気になることがあれば、いつでもお問い合わせフォームからどうぞ。
※ 本記事には筆者の体験談・感想・主観が含まれています。
効果や感じ方には個人差があり、内容はすべて特定の結果を保証するものではありません。
※ 一部の商品・サービスについては、アフィリエイトリンクを使用しています。
紹介によって報酬を受け取る場合がありますが、記事内容は公平性・信頼性を重視して構成しております。
※ 医療・健康・美容・副業・金融などに関する情報は、必ずご自身で複数の信頼できる情報源をご確認ください。
最新の状況やリスクについては、専門家への相談も推奨いたします。